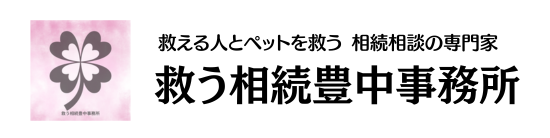"知らなきゃ損" ブログ
2025.10.12
加給年金って
知らなきゃ損 No 36
「うちの主人、最近“加給年金”をもらってるって言ってたけど、何それ?」
近所の友人からそんな話を聞いたことはありませんか?
加給年金(かきゅうねんきん)とは
簡単にいえば「年金をもらう本人に家族がいると上乗せでもらえるお金」のことです
*
意外と知らない方が多いのですが
条件を満たせば毎年数十万円が加算される制度なんです
*
老齢厚生年金を受け取る人に
一定の扶養家族(主に配偶者や子ども)がいる場合に加算される制度
つまり
「働いて厚生年金に入っていた夫が年金をもらうようになったとき
まだ奥さんが65歳未満ならその分が“加給年金”として上乗せされる」という仕組みです
*
たとえば
ご主人が会社員で厚生年金に加入していた場合
老齢厚生年金に配偶者加給がつきます
奥様が65歳になるまでは
年額約39万円が加算されます
*
次の3つの条件を満たすこと
1️⃣ ご主人が厚生年金(老齢厚生年金)を受け取る立場
2️⃣ 奥様が**65歳未満で、収入が少ない(年収850万円未満程度)
3️⃣ 奥様が生計を同じくしている(同居・生活費を共にしている)**
*
つまり
まだ奥様が自分の年金をもらっていない間(65歳まで)に
ご主人の年金に上乗せされます
*
奥様が65歳になると
自分自身の年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることができる
*
この時点で
ご主人の加給年金は自動的に終了です
ただし
奥様が自分の年金を受け取るときに
**「振替加算(ふりかえかさん)」**という形で
一部が引き継がれる場合があります
*
「振替加算」とは
→ ご主人の加給年金が終わったあとに
奥様の年金に少し上乗せされる制度です
(生年月日により金額は異なりますが、年間で数万円程度)
*
よくある勘違い
❌「妻が働いていると、もらえないんでしょ?」
→ パートや短時間勤務などで一定の収入内なら対象になります
(おおむね年収850万円未満が目安)
*
❌「夫婦どちらも年金をもらってるなら関係ない」
→ 奥様がまだ65歳未満なら
加給年金の対象になります
*
まとめると
「加給年金」は
夫婦のうち年上の方(多くは夫)が厚生年金を受け取り始めたとき
まだ年下の配偶者(多くは妻)が65歳未満なら、年間約39万円が上乗せされるありがたい制度
*
ただし
65歳になったら終了し
「振替加算」という別の形に移ります
*
とりあえず
「うちは対象かしら?」と思ったら
日本年金機構の「ねんきんネット」や
最寄りの年金事務所で確認できます
*
一つアドバイスを
年金事務所の職員も人間です
良好な関係でいろいろ聞くと
親切に教えてくれます
*
喧嘩腰に聞くと
必要最低限しか教えてくれませんよ
それは損ですよね
知らんけど!
2025.10.05
未来の自分を助ける準備って
知らなきゃ損 No 35
未来の自分を助ける準備って なんでしょうか
私はこれまで多くのご家族の
「相続」や「お金の整理」に関わってきました
その中でいつも感じるのは
認知症になってからでは遅い」という現実
*
私自身、65歳を過ぎてから、
少しずつ“変化”を感じるようになりました
「ほら、あの人…あの…えっと、名前が出てこない」
「これをやろう!」と思って立ち上がったのに
何をしようとしたか忘れてしまう
そんなこと、ありませんか
*
私も以前は「まだ自分は大丈夫」
と思っていました
*
でも
自分でも“あれ?”と感じる瞬間がある今
認知症は特別な病気ではなく
“誰にでも起こる日常の延長”なんだと
*
ある日
セミナーの準備をしている最中に
急に思いついた良いアイデアがありました
「これは絶対に書いておこう」と思ったのに
他の用事をしている間にすっかり忘れてしまったのです
*
その時、ハッとしました
“これはもう、他人事ではないな…”
*
それからは、
閃いたことや気づきをすぐメモに残します
小さなノートを持ち歩き
日々の記録を残す
それは単なる「忘れ防止」ではなく
“未来の自分を助ける準備”になっています
*
認知症になったら、実際に何が困るのでしょうか
*
これまで多くのご相談を受けてきて
私が見てきた「困った事例」は数え切れません
•病院で「お薬の名前」を本人も家族も分からない
•延命治療をどうしたいのか、家族が話し合いで揉める
•高齢の夫婦でどちらかが倒れても、もう一方が手続きできない
*
これらは、決して他人の話ではありません
“準備をしていなかっただけ”で
誰にでも起こりうることです
*
今からできること:「繋ぐノート」で“もしも”に備える
だからこそ、私は「繋ぐノート」をおすすめしています
*
このノートには
・かかりつけの病院や薬の情報
・延命治療や介護の希望
・緊急連絡先(1本目の電話を誰にするか)
など、“家族が困らないための情報”を書き残します
*
認知症のリスクはゼロにできません
でも、
「情報を整理して残す」ことは
今から誰でもできる安心の備えです
*
65歳の今、私も完璧ではありません
でも
だからこそ“備えることの大切さ”を身にしみて感じます
*
認知症は突然訪れるものではなく
「昨日と少し違う今日」に気づくところから始まっています
*
だからこそ
“気づいた今”がチャンスです
ノートに一行でも書く、
話し合いを一度でもしてみる
*
その小さな一歩が、将来の自分と家族を救います
未来の安心を繋ぐための最初のステップ
どうかあなたも、今日から始めましょう
*
分からないことは聞いてください
2025.09.20
とある井戸端会議①
知らなきゃ損 No 34
とある井戸端会議
*
昼下がりの喫茶店(hmc-cafe)で久しぶりに集まった
50代の3人
優子さん 恵さん 潤子さんが信託について話し始めた
優子 「ねえ 最近よく聞く家族信託とか遺言信託って結局どう違うのかしらね?』
恵 「私も気になってた!ちょと前に銀行で遺言信託を勧められたの。でも手数料が高いって聞いて…。」
潤子 「じゃー今日は3人で整理しましょうか。まず家族信託ね これは家族で財産を預けて管理する仕組み メリットはねー」
*
家族信託
メリット:
柔軟な財産管理・資産承継の組成が可能
信託報酬を自由に設定可能 ランニングコストを抑えられる
財産であれば何でも信託財産にできる
*
デメリット:
受託者として 適任者がいない
受託者になった者に信託そのものの理解不足
受託者の不正や暴走を防ぐ対策に公的機関がない
受託者個人に交代のリスク(死亡・辞任)
家族関係が良くないとダメ
優子「なるほど 家族の安心のためだけどちゃんと専門家に相談しないとダメね」
*
商事信託
メリット:
プロの免許、登録を受けた受託者の管理
金融庁監督の下で 不正や相続リスクの低下
ご本人の死亡後の資金の引き出しがスムーズ
財産管理の負担軽減
長期間の信託が可能
*
デメリット:
管理にコスト(信託報酬)がかかる
受託者による権限が少ない
資産によって信託できないものがある
資産の組み換えといった柔軟な対応ができない
*
遺言信託
メリット:
遺言の作成・保管・執行鵜をまとめて任せられる
公正証書遺言
専門家が手続きを代行
*
デメリット:
手数料や管理料が高額になる
銀行のサービス範囲
トラブルの可能性あれば無理
*
潤子「費用を気にしなければ 亡くなった後の安心感は大きいわね」
優子「結局家族信託は生きている間の安心 商事信託はお金を増やす仕組み 遺言信託は亡くなった後の安心ってことね」
恵 「うん、どれも役割が違うのね大切なのは自分と家族に合ったものを選ぶことかも」
潤子「そんな時は 繋ぐライクファミリーサポートに相談したらいいって聞いたことあるわ 全国組織だし安心よね」
恵「あーそれ 繋ぐノートを作ったとこよね」
潤子「そうそう」
*
3人は顔を見合わせて
なんだか安心したように笑いました!
わからないことは聞いてくださいね
2025.09.13
とある井戸端会議
知らなきゃ損 No 33
とある井戸端会議
昼下がりの喫茶店(hmc-cafe)で久しぶりに集まった
50代の3人
優子さん 恵さん 潤子さん
*
優子さんが不意にため息をつきました
「この前、母が急に倒れて救急車で運ばれたの
病院に着いたら先生に持病は?
薬は?と聞かれたんだけど…全然答えられなくて
もう頭が真っ白」
*
恵さんは驚いた顔
「それは大変だったでしょう?
お母さん 大丈夫だったの?」
*
なんとか助かったけど…
私がもっと知っていたら、
もっとスムーズに治療してもらえたのかなって思って
あの時は本当に悔しかった」
*
そこで 潤子さんが口を挟んだ
「そういえば、この前ネットで見たんだけど
『救う相続』ていう名前の事務所があるの
ちょっと変わった名前よね
救える人を救うって意味なんだって」
*
恵さんが首をかしげる
「相続って”お金や財産のこと”ってイメージだけど
救うってどういうこと?
*
潤子さんはスマホを見ながら続けた
「その事務所の先生、元は救急救命士だったんだって
命の現場で情報が分からないせいで助けられない人をいっぱい見てきたから
「相続の仕事でも生きている人を救いたい」って思ったらしいの」
*
優子さんが思い出したように言いました
「そうそう、その先生が作った『繋ぐノート』っていうのを私も書いたの
これがね、エンディングノートと違って”今すぐ役立つ”ノートなのよ」
*
恵さんが興味津々
『どんなこと書くの?」
*
「例えば、救急車を呼んだ時最初に誰に電話するか、とか
飲んでる薬、かかりつけのお医者さん
入院したら必要な生活のこと
延命治療をどうしたいかまで
家族が迷わないように、まとめて書けるの」
*
潤子さんは、うなずきながら言った
「なるほど、それがあれば家族も安心だし
本人も『伝えておけた』って気持ちになるわね
*
コーヒーを飲み干した恵さんがぽつり
「そういえば、私、もし夫が倒れたら…
誰に電話すればいいんだろう
子供も遠くにいるし」
*
優子さんが微笑んで答えました
「だからまずは”1本目の電話は誰にするか”って書いておくのが大事なのよ
それだけでも『繋ぐノート』の最初の一歩になるから」
*
3人は顔を見合わせて、
なんだか少し安心したように笑いましたとさ!
*
わからないことは聞いてくださいね
2025.09.03
老いを楽しむとは
知らなきゃ損 No 32
老い という言葉
あまりいい印象は
ないのではないでしょうか
*
人生100年時代と言われて久しいですが
医学の進歩や生活環境の変化で
昔よりずっと長生きになりました
*
その長い人生
どう過ごすかというと
不安を抱える人は多いのでしょうか
*
ある夕方の電車の窓に
ふと映った自分の姿を見て
私はハッとしました
*
「え、こんなに白髪が増えていたの?」
顔に刻まれたシワ
少し疲れた表情
*
かつての自分と比べて
落ち込んでしまいそうになりました
でも同時にこれは誰にでも訪れる自然なことなんだ
と思い直すことができました
そのきっかけとなったのが「老い本」です
*
老いを特別な不幸ではなく
誰もがたどる自然な流れ
若い頃になかったシワや白髪は
実は自分の人生の証
*
こんなに長く頑張ってきたんだと思うと
むしろ誇らしく思えます
*
今の年齢だからこそ
味わえる贅沢があります
*
仕事や子育てに追われていた頃にできなかった趣味を再開したり
友人と昔話をして馬鹿笑いしたり
年齢を重ねたからこそ
心から楽しめる時間があります
*
それでも、
老いを考えるとどうしても不安はつきものです
健康のこと、お金のこと、家族のこと・・・。
*
やはり準備があると安心ですよね
私自身も繋ぐノートに緊急時の連絡先や
延命治療の希望を書き留めています
*
これを整えておくと
老いもただ怖いものではなく
安心して次のステージに進むための通過点に思えます
*
電車の窓に映る自分の姿に
ショックを受けたあの日
*
けれども今は
その姿を「これからの自分への入口」と思える様になりました
老いを悲しむのではなく
豊さのきっかけとして受け入れれば・・・。
*
人生の折り返し地点
どう楽しむかですね
分からないことは聞いてください
2025.08.30
認知症の対策とは
知らなきゃ損 No 31
認知症と聞くと
どこか遠い話に感じる方も多いかもしれません
*
でも実際は
50代・60代の今から準備をしておかないと
いざという時に
家族が大変な思いをします
*
こんな話があります
ある日 母が認知症になった話です
*
「スーパーで財布を落としたみたいなの」
ある日、母からの電話です
慌てて駆けつけると
財布はカバンの奥に入っていました
その時はホッとしたものの
私は小さな不安を感じました
*
その後
冷蔵庫に牛乳が3本並んでいたり
ガスコンロの火がついたままになっていたり・・・。
*
「ちょっと心配だな」と思いながらも
まだ大丈夫だと
自分に言い聞かせていました
*
そんなある日、母が転んで骨折し
入院します
入院の際は問診票を書かないといけません
*
持病は?
飲んでいる薬は?
と聞かれても、母は答えられない
私も正確な情報を知らず 慌てるばかり
*
さらに銀行では
「代理でお金を下ろすには、
後見人の手続きが必要です」と言われる
生活費すら動かせず
本当に困ってしまったんです
*
認知症になると
どういうことに困るんでしょうか
*
認知症になると困ることは
飲んでいる薬や持病が分からない
本人の希望(たとえば施設か在宅か
延命治療を望むのか等)
*
こうした問題は
ある日突然やってきます
どうすればいいんでしょうか
*
まず
解決策の一つに
繋ぐノートがあります
*
もし元気なうちに繋ぐノート
に記録していたらどうでしょうか
- かかりつけ医や薬の情報
- 生活状況 担当ケアマネなど
- 介護や延命治療の希望
これらを書いておくだけで
家族は迷わずに対応できます
本人も「自分の思いを伝えられている」
という安心感を持てます
*
認知症は
誰にでも起こりうることです
大切なのは
「まだ大丈夫」と思える今から備えること
*
繋ぐノートは、
未来の自分と家族への“思いやりの手紙”のようなもの
*
小さな準備が
将来の大きな安心につながります
*
「自分のために、そして家族のために」
今日から少しずつ、備えを始めてみませんか
*
#お問い合わせ
2025.08.25
在職老齢年金の改正
知らなきゃ損 No 30
在職老齢年金制度について改正されました
何それって話ですね
*
60歳以上で働きながら
厚生年金をもらうと収入が多い場合
年金が削られます
*
これが在職老齢年金です
「在老」 とも言われます
*
この「在老」が変わります
そもそも「在老」って何でしょうか
*
月額賃金(1か月の賞与を含む)と厚生年金を足した額が
基準額を超えると厚生年金は超えた分の半額が
支給停止になります
*
基準額は毎年見直され 2025年は51万円
51万円を超えると
超えた分の半分が年金から差し引かれます
*
つまり51万円までは全額とれて
それを超えると調整が入ります
*
例で説明します
基本月額:10万円
総報酬月額相当額:45万円(給与➕賞与を1ヶ月に換算)
月額
55万円(55−51)÷2=2万円
*
受け取り年金は
10万円ー2万円=8万円
*
そして
2026年度(令和8年度)4月から
62万円に引き上げられます
つまり
61万円までなら年金はそのまま受け取れ
62万円を超えた部分のみ調整されるようになります
*
なぜ変更されたのでしょうか
それは
平均寿命や健康寿命が伸びたことで
高齢になっても働きたい方が増えています
一方で年金が減ってしまうことが働き控えの原因になりかねませんでした
*
つまり
「今までは働きすぎると年金が減っちゃって」
でも改正後は“ちょっとの収入アップなら年金そのままって嬉しくなりますよね
副業やパート、再就職を考えている方に対して
「月60万円未満なら年金に影響なく働けます」
高齢になっても働き損を気にせず
活躍したいですね
2025.08.16
繋ぐノートは、福利厚生の一つ
知らなきゃ損 No29
繋ぐノートは会社の福利厚生になります
え、どういうこと?って感じですよね
福利厚生といえば
健康診断や休暇制度
子育て支援などを思い浮かべる方が多いと思います
*
でも
今は “働きやすさ” だけでなく
“生きる安心” まで会社がサポートする時代になってきました。
*
それでは
繋ぐノートには何が書かれているのでしょうか
*
繋ぐノートは
もしもの時に生きる準備を書き留めるノートです
*
たとえば
- 緊急連絡先(一番最初、誰に連絡するのか)
- 持病や服用中の薬、かかりつけの病院
- 入院時の生活情報(食事の好みや制限、必要なケアなど)
- 介護に関する情報(ケアマネージャーの連絡先や介護度)
- 延命治療についての希望(本人が望むかどうか)
*
これらが一冊のノートに書かれていたら
急な病気や事故のときでも
医療や家族の対応がスムーズになります
その結果、救える命が救われます
*
もしも
会社が繋ぐノートを用意してくれたら…
想像してみてください。
*
あなたの働く会社が、
繋ぐノートを福利厚生の一つとして用意してくれたら
*
しかも
従業員本人だけでなく
ご家族にも書いてもらえるようサポートしてくれたら
たとえば、お父さんやお母さん・・・。
*
「この会社は、自分だけでなく家族を本当に大切にしてくれている」
そんな安心感が生まれます
*
安心感は“会社への愛”につながります
働き続けたい気持ちを高め、離職を防ぎます
*
また、
「この会社で働きたい」と思う人が増え
採用にもプラスになります
*
繋ぐノートは、単なる紙や記録ではありません。
会社と従業員、そして家族をつなぐ“信頼の証”なのです
繋ぐノートを使わない理由が見つかりません
*
繋ぐノートは
社団法人 繋ぐライクファミリーサポートが開発しました
*
分からないことは聞いてください
2025.08.01
遺言書の表現って
知らなきゃ損 No28
遺言書で使用する言葉って
堅苦しいイメージがありますね
普段使わない言葉が使われますからね
*
たとえば
「妻に自宅を相続させる」という言葉
ふつうの会話ではこれだけで十分通じますが
遺言書としては、もっと詳しい情報が必要です
*
最低限、自宅の土地・建物が特定されないといけません
特定されないと
名義変更もできない可能性があります
*
遺言書にはある程度決まった表現があります
相続人には「相続させる」
相続人以外では
「遺贈する」という言葉を使うのが基本です
*
これを間違って
相続人に「遺贈させる」と書いてしまうと
遺贈扱いになり不動産がある場合は
登録免許税が高くなる場合があります
*
また
遺言執行者が書かれていない場合
遺言者が亡くなった後
家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらったりする場合があります
*
たとえば
「遺言者の夫が妻へ全財産を」
という内容を書いても
夫より妻が先に亡くなると
妻に渡そうとした財産は宙に浮いてしまいます
*
妻が先に亡くなった場合
「長男に」(予備的遺言と言います)と書いていれば
長男に渡せますが、書いていなければ
宙に浮いた財産は遺産分割協議の対象になります
*
このように
最後まで遺言書の内容通りに実行できるように
あらゆる可能性を考えた予備的遺言を
含めて作成することが大切です
*
どうですか
せっかく遺言書を書いても
かえって揉める原因にならないようにしないとね
*
分からないことは聞いてください
2025.07.28
明朗って
知らなきゃ損 No27
明朗っていいよね
私は週2回 スイミングスクールに通っています
大人の習い事ですね
*
スクール生の中では
私は若造になります
*
ほとんど年上なんです
しかも女性の方が多い
*
そして
みなさん健康の意識が高い
男性よりも意識が高いのかもしれません
実際 女性の方が長生きだしね
*
先日、マスターズスイム大会に参加しました
年齢別で一緒に泳ぐんですが
みなさん自分の目標タイムとの戦いです
*
私も挑みましたが
タイム更新はならず悔しい思いです
*
スタート前、待機の際
スタート台に立った男性の姿が
まわりと違っていました
*
少し前傾で
いつ構えるのかなーという感じですが
動きません
*
スターターもタイミングを見ていたのでしょう
しばらくスタートの合図はなく、静寂の時間
そしてスタートの合図
*
飛び込んだ男性は明らかに遅い
何げに
電光掲示板を見ると
年齢がなんと95歳と表示
*
他の選手が全員ゴールした時
残すところ20m
そしてゴール
拍手👏
*
私がもし同じ年齢まで生きれたら
同じことができるだろうか
無理かな
*
いや
自分で限界を作ってはいけませんよね
今日は、記録更新はできませんでしたが
生きる元気は貰いました
*
彼はきっと
前向きな笑顔の絶えない毎日を送っているに違いない
*
そういえば
今通っているスクールでも
笑顔が素敵な高齢女性がいます
彼女の年齢は88歳です
背中も年相応に曲がっています
*
おそらくジムの中では
最高齢でしょう
いつも熱心にスクールに入り
上手く泳ごうと研究熱心です
*
私は彼女に会うとき
「今日もご機嫌うるわしゅう」と声をかけ
「ボーイ」と彼女は私を呼び
ハイタッチします
*
冗談を言い合って
バカ笑いします
今は
彼女を笑かすのが私の楽しみの一つです
*
明朗っていいよね
何歳になっても
私は彼女に出会い
明朗でいようと決めたのかも
*